株式会社セルティア
「ふるコネ」のプロジェクトに見る創出の喜びと
小さくとも「世の中を変えている」という実感
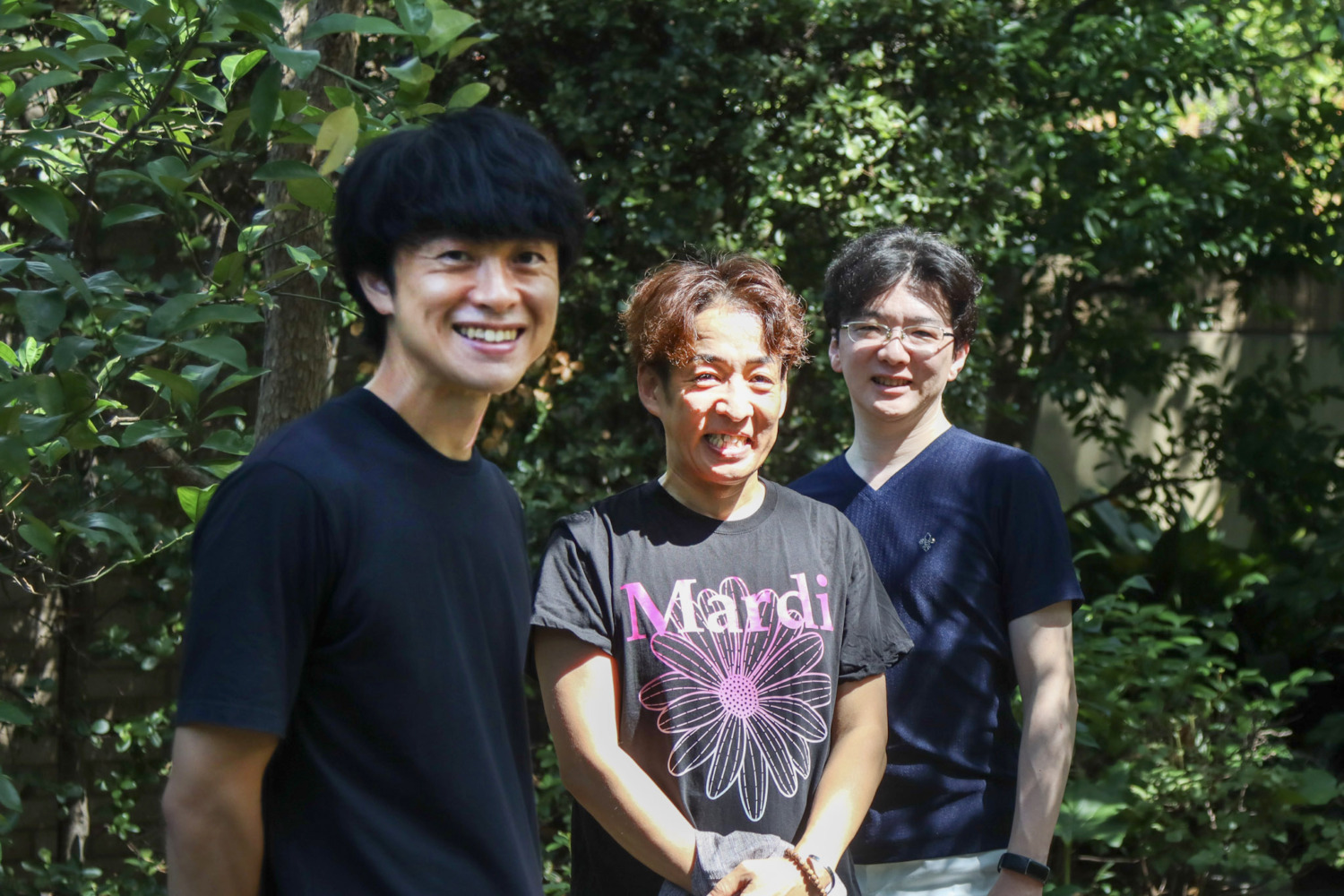
株式会社セルティア
最先端の技術と革新的なアイデアを活用し、多様な業界に向けたソリューションを提供するクリエイティブカンパニー。オーダーメイドのソフトウェアやプラットフォームの開発やデジタル変革支援を通じての課題解決、事業成長支援を得意とする。JTBの企業版ふるさと納税プラットフォーム「ふるコネ」の開発会社としてカルティブと連携。
インタビュー
株式会社セルティア 梶原様、鷹股様
株式会社カルティブ 池田
持っている知識や経験でー
「ふるコネ」でどこまでできるのかを試したい。

自己紹介とセルティアの紹介をお願いします。
- 梶原
- セルティア代表の梶原と申します。セルティアは「コンテンツシステム開発、運営」をメインに”面白そうなことあったら何でもチャレンジしていこう”という会社です。創業5年、社員数は現在8人。みんなものづくりをする人間でメンバーそれぞれに得意とするコンテンツがあります。コンテンツ制作とシステム制作っておなじものづくりでも違うものだと思うんですけど、その両方ともを作る会社です。
- 鷹股
- セルティアに営業として入社したんですが途中から自社で何か作っていこうという話になった時にWEBの制作に携わるようになって、そこからフロントエンドエンジニアとして仕事をしています。ゲームのコーディングや運用ディレクションなどにも関わりました。
カルティブと知り合ったきっかけは何ですか?
- 梶原
- きっかけは徳永さんです。彼は私と昔いた会社が一緒だったんです。その縁でWEBのご相談をいただいたのが2020年です。
- 鷹股
- JTBのプロジェクトの「ふるコネ」を作る時にセルティアにお声掛けいただき、私がチーフディレクターとして参画しました、仕様の検討、経営側の人たちと連携、進捗管理などを担当し、現在もそういったディレクション業務を継続させていただいております。
ふるコネのプロジェクトにおいて、カルティブはどういう立場だったんですか?
- 池田
- 「ディレクターである鷹股さんを動きやすくする」というサポートが大きかったです。
予算の調整やJTB側の体制の交通整理、ちょっと特殊な調整も多かったです。事業企画から行っているという立場からブリッジの役割でした。基本設計以降の工程はほぼ鷹股さん。こちらはたまに判断の背中を押すぐらいでした。 - 鷹股
- ふるコネはシステムの規模もすごく大きかったし、調整することも多かったので一筋縄に行かなかったというのがあります。この体制で2020年の12月からふるコネのプロジェクトに着手し、翌年4月にphase1が完成。2024年まで運用していました。
それまでにあったWEBサイトをゼロに戻すところからはじめ、「安定した運用」を実現するためというのがphase1の課題でした。ローンチの後も、不安だよねっていう処理がシステム側にはあったので定期的にその改修にメスを入れていました。システムが安定してきたら次はWEB側、phase2やphase3はSEOチューニングやキーワード戦略などを行いました。phase4は今使っているフレームワークや、PHPのバージョンなどそういったものをしっかり保守する体制を作りましょうということで、システムのメンテナンスの最適化に注力しました。
その後、JTBさんのほうで企業版ふるさと納税の事業面の位置付けを再検討がはじまって、決済機能は外しましたが、それまではおなじチームで進めていました。
ふるコネのプロジェクトにおいて、一番大変だった時期ってどの時期でした?
- 鷹股
- 1つ目は、リリースです。時間的な拘束が多かったけど、やはりリリース直前は土日返上かつ、朝からずっとオンラインでつなぎっぱなしでした。何か仕様変更があったらすぐにできるような体制で、1週間ぐらいはそれに近い状態でエンジニアもその体制で開発に臨んでいて、「何を削って何を出すか」を現場で判断する連続が大変でした。
もう1つは、プロジェクトの後期、WEBサイトをどうしていこうか?続けてるのか、やめるのか?という議論です。ふるコネのビジョンがモチベーションになってたので精神的に少し辛かったです。持っている知識や経験をJTBさんのこのサイトでどこまでできるのかを試したというのはいい経験でした。 - 池田
- 一番最初にお二人に参画するかどうかを尋ねたときに、そうおっしゃってくださいました。「持っている知識をこのプロジェクトで試したい」と言っていただいて「声をかけてよかったな」と思いました。

バランス感覚と理解の速さがもたらす安心感
カルティブのメンバーの印象をお願いします。
- 鷹股
- 徳永さんの印象としては、ものすごい仲良くコミニュケーションをとってくれる、気さくな方だなと感じました。
- 梶原
- 池田さんは「わかってくれる」安心感があります。飄々としていて、何事にもすごい柔軟で、風通しがいい。そんなふうに気を張ってないようにみえて、要所を的確に抑えているという印象です。また、知的な一面と同時に人間的な温かさもすごくあるんです。ビジネスのセンスも抜群でいるのに、バランス感覚が本当にすごいなって思っています。
技術サイドの仕事をされてきたかと思うんですけど、プロジェクトの進め方や目的に対する理解が深くて、開発の流れをちゃんと分かってくれてるのがめちゃくちゃ助かります。例えば、不具合が出たときも「こういうのは起こるもんだから、こうやって乗り越えよう」って冷静に言ってくれるから、現場としてはすごく心強いんです。
ビジネスで人間関係を作ったりアイデアを推したりする力と、技術を理解してサービスを作る力って、全然別物だと思うんですけど、池田さんはその両方ができてしまうのです。それが本当にすごいところだなって思います。普通だったら開発の工程を一つ一つ説明しないといけない場面も多いんですけど、池田さんがいると、しっかりとすぐ理解していただける話が早いんで、本当に仕事しやすいし楽しいです。
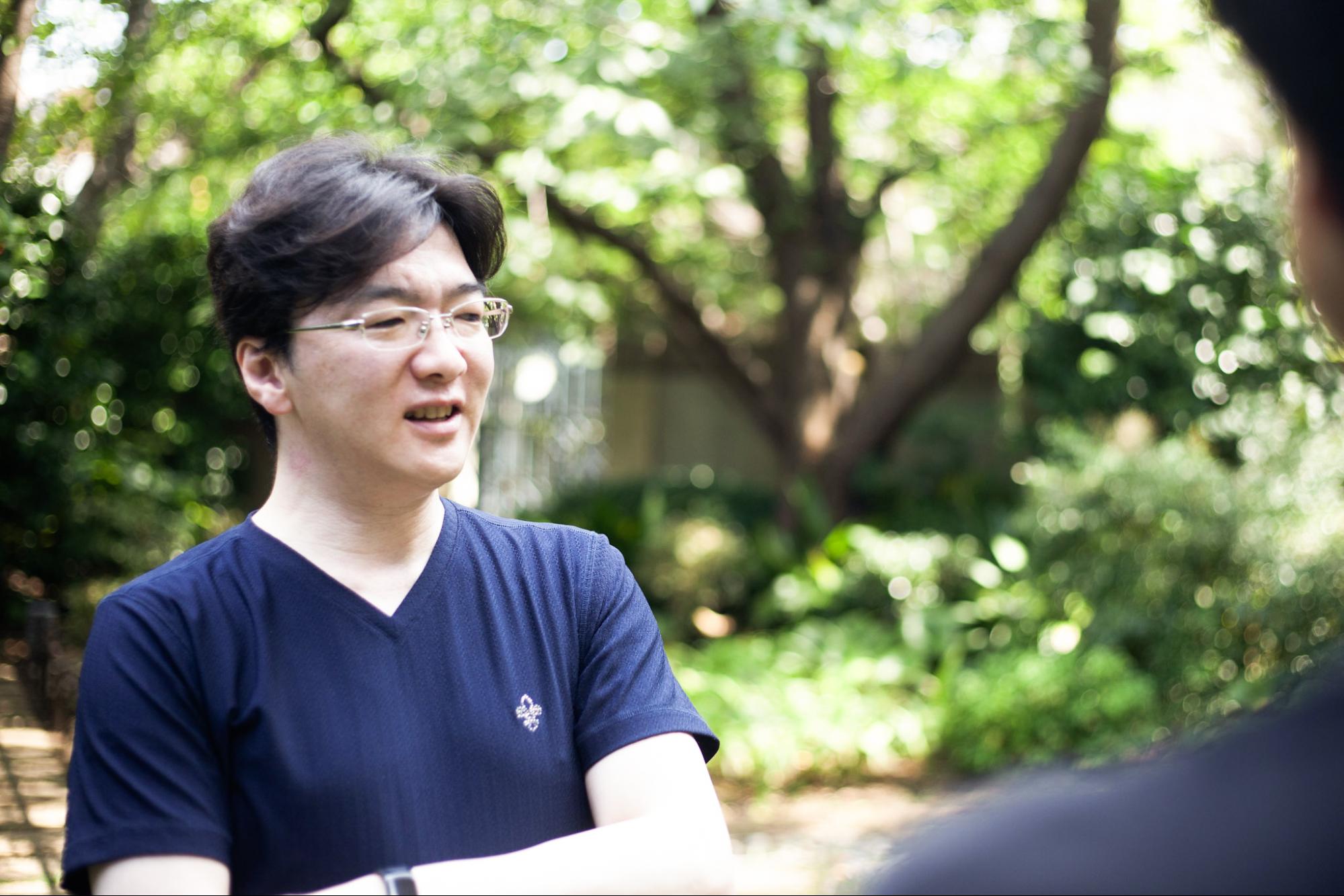
カルティブから見たセルティアの印象を教えてください。
- 池田
- 梶原さんは、やはりアイディアマンです。枠に囚われることなく企画を考えられるため、ゼロイチを生み出す力に優れています。一方、鷹股さんはディレクションを安心して任せられる頼もしいプレイヤーです。大型プロジェクトにも対応できるディレクターやPMとしての高いマネジメントスキルを備えています。現場視点での優れた技術力と、体系的に俯瞰してプロジェクト全体を見渡せるスキルの両方を兼ね備えており、自身で手を動かすこともできますが、あえてそれをせず、チームが円滑にプロジェクトを進められるように立ち回ります。また、リスクマネジメントの感覚も鋭く、事前に障壁を取り除いてくれる点でも非常に頼りになります。
セルティアの組織については、梶原さんがアイディアを出し、それを鷹股さんがきれいにまとめるという役割分担が確立されています。そのスピードは非常に速く、両者のバランスが取れた素晴らしい会社だと思います。お互いの高い能力を最大限に活かし合い、組織としての成果を最大化している点が特に印象的です。
想定以上に規模が大きくなったプロジェクトを
運営していく楽しさがある。
ふるコネのプロジェクト以降はどういう予定がありますか?
- 鷹股
- 今一緒にプロジェクト開発させていただいているのは「ロケふる」というサービスで、2025年にサービス開始される予定です。ふるさと納税ができるアプリです。こちらのプロジェクトは、2024年の3月か4月からの着手でした。WEBサイトとアプリの違いがあって、また考え方は違うんですがふるコネで培った知見があったので、イメージが湧きやすかったです。
ふるさと納税ならではの仕様もあり、買い物を楽しみたいのに、「ワンストップ」などちょっと聞き慣れないことを聞かれると障壁になってしまう。ちょっとした設計でユーザーを煩わしくさせてしまう点に注意を払いました。
このプロジェクトは仕様もなるべくシンプルに使用するユーザーが分かりやすいように最初は機能をあまり詰め込まず、開発同様にシンプルに進めました。限られた時間の中でやれることをやって、ここから機能を付け足していくイメージです。 - 池田
- 梶原さんや学さんは、カルティブとしては近くにいたいパートナーです。このプロジェクトがなくなったから関係解消というふうにしたくないと思っています。お互いそう思ってくれる関係で連携していきたいと考えています。ふるコネのプロジェクトは終了しましたが、それに替わるぐらいのいい仕事をしようと思っています。
ロケふるに関してのモチベーションはなにですか?
- 鷹股
- ふるさと納税の市場が成熟してきている中で、隙間の部分を狙っていく点は面白いなと思います。そこからの広がりも、会議に参加させていただきながらワクワクします。
自分が思ったより規模が大きくなっていて、それをみんなで運営していくのが、純粋に楽しいです。作って終わりじゃなくてリリースした後もそのアプリが活用されていくようにがんばります。
何かを世の中に出せる喜びと興奮が今後も継続できたら

- 鷹股
- 何か新しいことをやるときはもう一回技術選定し直すんですけど、その時に「今こうやったらもっと円滑にいいものが構築できる」と思えます。それはモチベーションになります。
- 梶原
- 新しいチャンスにチャレンジしていけるっていうのが楽しくなる最初のポイントです。もう一つ、リリースしたタイミングでユーザーの反応が出てくる。まあユーザーの反応をなるべく出してもらうように仕向けてもいるんですが、そのタイミングっていうのもすごい楽しいところです。ワクワクする。ふるコネはSEOの強さもあったから、数値として可視化できるところが多くて楽しかったですね。寄付の額が急に伸びたり、SEO対策したページが上位に位置したり、やったらその分ちゃんとついて来るというのがモチベーションです。
今後、カルティブに期待することを教えてください
- 池田
- 私はみんなが笑顔でいる限り、末長くどんどんプロジェクトをやっていきたいです。
技術のトレンドを追い続けてくれているので、そこを提供していただける点でもご一緒にやっていくことになるんだろうなと思っています。 - 鷹股
- カルティブは私の見えてない視点をビジョンにもっていらっしゃると思います。私が持っている力と組み合わせて、何かを世の中に出せる喜びがあります。そういう興奮が今後も継続できたられたらうれしいです。
- 梶原
- やはり世の中に影響を与えられるのが面白いですね。少しだけでも世の中変えてる手応えが感じられるとしあわせです。カルティブの皆さんと一緒に、今後も私たちの頑張りを広げていけたらと思います。

