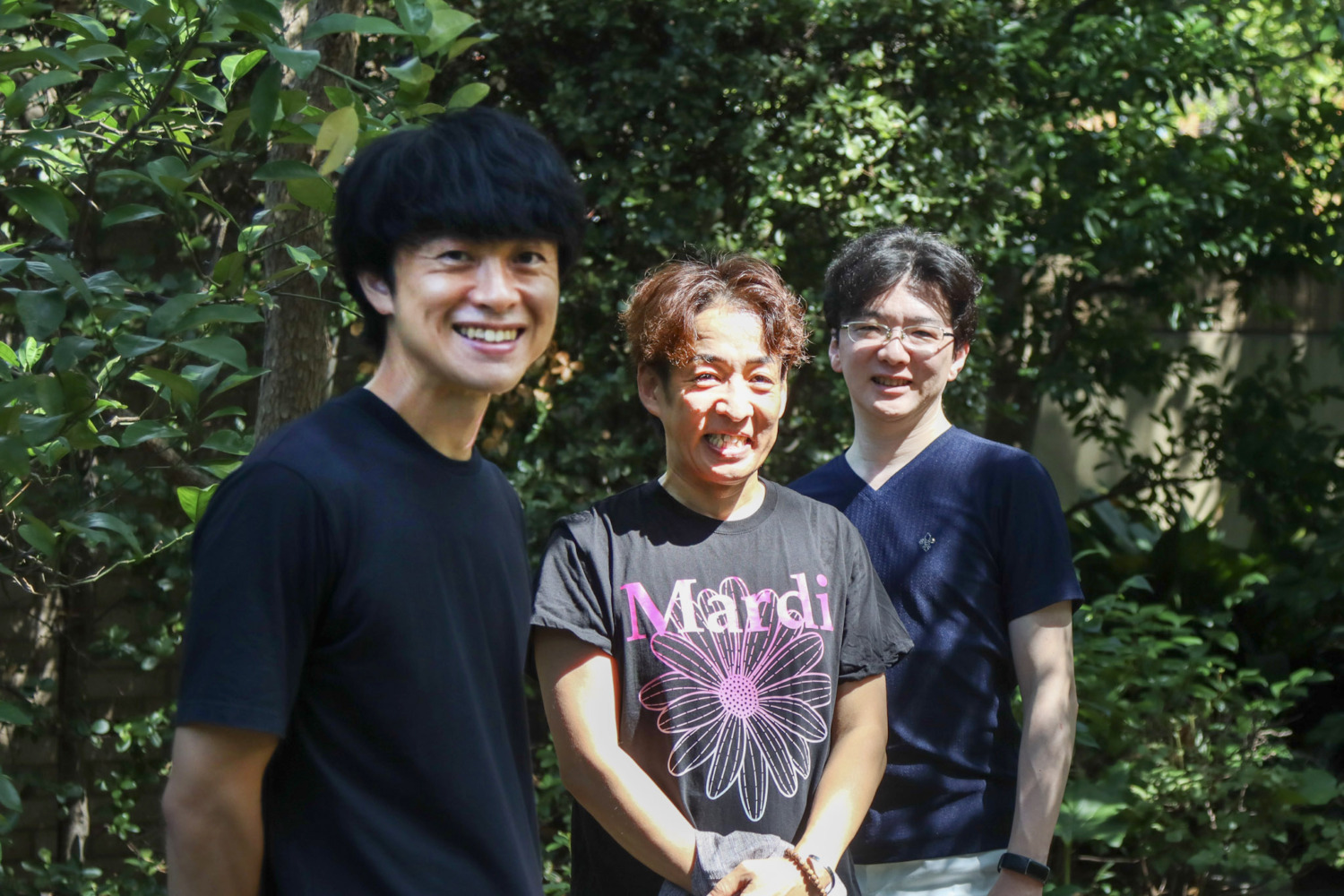株式会社アイディエーション
一緒に作ったレポートで市場を大きくするのが面白い。
企業版ふるさと納税の調査に見るプロフェッショナリズム

株式会社アイディエーション
マーケティングリサーチとワークショップを強みとして、企業の商品・サービス開発を支える企業。定性調査から定量調査まで幅広く企業のニーズに合わせた調査メニューを展開する。カルティブとは企業版ふるさと納税の活用意向調査で2021年度より提携している。
インタビュー
株式会社アイディエーション 坂田様、波多野様
株式会社カルティブ 小坪

この後市場がどうなるかも全く分からないような調査を
面白がってやってくれる会社はないかな?
アイディエーションさんの紹介をお願いします。
- 坂田
- アイディエーションはマーケティングリサーチの会社です。
定量調査、定性調査、量的な分析と質的な分析と両方行う会社になります。他にもいろいろ調査メニューがあり、総合的に何でも対応できます。
カルティブさんから依頼されている件は、その中の定量調査です。
リサーチコンサルティング部という部署は、そのメインの調査業務をしている部署です。
カルティブと会ったのはどのタイミングですか。
- 坂田
- 4年前くらいです。2020年の10月に入社し、最初の調査が2021年の1月でした。私がジョインしたのは2021年の7月でちょうどそのころに2回目の調査がありました。
- 小坪
- 初めての調査のときにはまだ坂田さん、波多野さんは入社前でして、役員の倉澤さんと一緒に調査設計を行いました。riverの北関東支社である新朝プレス代表の髙嶋さんよりご紹介いただき、協働が始まりました。
坂田さんは、2回目の調査からですよね。 - 坂田
- 私はもともと銀行の営業をやっていましたが、中途でアイディエーションに入社しました。その時は役員3人しかいおらず、代表の白石、山川という副社長がいて、あとは白石兄がいました。その3人に今のマネージャー2人という5人の会社でした。今は結構人が増えました。アルバイトを入れて従業員は30人ぐらいですがそのうち社員は17人、来年1月には20人になる予定です。
- 小坪
- 順調に成長中の超優良な企業だなぁと思っています。
「こういう調査をやりたい」というのを2020年夏頃から思っていました。その当時は自治体側も企業側も企業版ふるさと納税の制度を全く知らない状況だったので、このマーケットがどう成長するかも正直不明瞭でした。
認知度が全く拡がっていないからこそ、浸透率をふくめて毎年定点調査がやりたかったんです。「この後市場がどうなるかも全く分からないような調査を面白がってやってくれる会社はないかな」と。
業務として淡々とこっちから言われたことをやるよりも、前提として「この市場が大きくなってくれるのを望んでいる人」「どうやったら大きくなるかを一緒に考えてくれる人」とやりたいと思いました。そこで何人かのriverの支社長に声を掛けた時に髙嶋さんが紹介してくれました。最初、倉澤さんと白石さんと高嶋さんと僕で打ち合わせをした時にゼロベースのところからすごく前のめりに面白がって加わっていただきました。
1回目の調査は本当に大変で、自治体・企業それぞれが、認知・関心・検討・実施までにどういったフローをたどるのかということを市場形成やマーケティング、アンケートの視点で仮説設定・検証・設問設定を繰り返しました。たとえば、自治体の状況を「挑戦層」「継続層」「消極層」「離脱層」の4つのカテゴリーに分けて、それぞれの成長フェーズを定義したり成長要因を分解するための設問設定をしていきました。 - 小坪
- 定点で、毎年同じ設問構造で継続して収集・分析したく、できるだけ時代とともに変わらないようにしたいというので何度も打ち合わせをさせてもらいました。
「多分こういう方向でマクロの市場は成長していくだろう」というストーリーを立てたんです。今回、こういう質問を当てると、多分こういう回答が来て、そうしたらこういう風に普及啓発活動を展開しよう…みたいな市場形成・マーケット展開のシナリオ作成、仮説検証までを一緒に考えて、提案していただきました。
上記からも分かる通り、アイディエーションの一つの特徴として事業コンサルに近い視点をしっかり持ってくれていると思っています。出てきたアウトプットがどう事業や市場形成に活かせるのかみたいなところを結構重要視してくれて積極的に提案してくれているんですね。そこがやりやすい一つの特徴かなとおもいます。単純にこう調査をやりまして調査結果がこうですみたいな感じではないと僕は思っています。 - 坂田
- そうですね。小坪さんに対しては、特に提案が増えています。
全クライアントに対して「リサーチだけで終わらない」ようにしています。そこからアクションプランを練るわけなので、それに繋がるような提案というか示唆出しをレポートでするようにしています。 - 小坪
- 最初に紹介を受けた時から髙嶋さんからそう言われていました。「一緒に市場を作っていこう」とか「一緒に作ったレポートで市場を大きくするみたいなのが面白いよね」というのが根底にずっと残っていますね。

坂田さんがジョインされたとき、riverに対してどういった印象を持ちましたか?
- 坂田
- 何をやってるか分かりませんでした。今も不明瞭な点は色々あります。プラットフォームを運営していると聞いていました。けど実際は「何でも屋」なのだろうなと。
「広い」んです。そこがメインかと思っていたら、カルティブって全体でもっといろんなことをされていますよね。いろいろやっているんだよなぁと思いながら毎回HPを見ています。 - 波多野
- 今更ながら、質問になってしまうんですが、調査を一緒にやっている石野さんはどういう方なんですか?
- 小坪
- 石野さん(調査の協働メンバー)はriver事業における地域支社のメンバーです。
riverは、7支社と共同運営なんですけど、「支社とカルティブに上下は全くなく、完全に分担し事業を大きくしていきましょう」という話になっています。その中に「市場調査」というのがあります。この調査事業は、river事業を大きくする上で重要な施策になっているので全社で協力してちゃんと成功させましょうという位置づけですが、プロジェクトメンバー20人くらいいる中でも一番この市場調査に特性がマッチするのが石野さんだと考えており、参画してもらっています。石野さんは、自治体とのやり取りや他の地域支社の統括をしたりしています。情報の取りまとめやデータ整理などもやってくれます。石野さんはご自身でここ数年、統計を勉強して資格を取り、その知見を活かしてくれています。もともと営業を長く経験されておられるので、自治体・企業ともに現場の肌感覚もとても鋭く調査に活かしてくださっています。
石野さんのようにriverには尊敬できるメンバーが本当にたくさんいます。 - 坂田
- 私が石野さんと一緒に行った内閣府委託事業の調査の話ですが、内閣府の持っている寄付データと調査データを連携させて、分析しようとしたことがありました。
元のデータを見ていたらあるデータがおかしいことに気づきました。納期の一日前でしたが石野さんにその報告を深夜に送ったらすぐ「確認します」という返信が来ました。その数時間後に修正校が来て、対応するフットワークの軽さに驚きました。

アイディエーションって東京本社と愛媛支社という珍しい形態ですが。どういった理由なんですか?
- 波多野
- 社長の白石が愛媛出身なのですが、「地元に貢献をしたい」という思いから愛媛支社が設立されました。私は現在、愛媛支社で働いているのですが、その白石の想いに惹かれて応募しました。
当時の面接担当の1人に坂田がいたのですが、ほぼ同い年にも関わらずとても堂々としていて、憧れを感じました。また、地方にいながらマーケティングや東京の大手企業を相手に仕事ができることが面白そうだなと思い入社したいと強く思ったことを記憶しています。 - 小坪
- アイディエーションのように、産業とか経済といった事業活動、雇用を通じて地元の人や地域に経済的還元があるという流れに僕は惹かれます。アイディエーションは、そういう取り組みをたくさん取り入れておられますし、その点でも共感します。
- 坂田
- カルティブとの調査は、例年5月頭に1回目の打ち合わせをして、6月中旬から7月末までをアンケートの回収期間としています。自治体は回答期間が長いほうが回答数も多くなります。7月末に回答受付を終了し、8月でレポートまとめて9月に報告会。だいたいこの流れです。
- 小坪
- アイディエーションと一緒にやっている感覚でお願いしているというところもあるので市場の変化とか事業の変化というのを最初にちゃんとインプットするように心がけています。定点調査なのでできるだけ設問を変えたくないのですが、市場や事業の変化に基づいて最低限変えたほうがいい部分の認識合わせをだいたい1回目にします。石野さんにもその時には必ず参加いただいています。5回目にあたる去年の調査で、質問構成を大きく変えたんですよね。
- 坂田
- 最近だと、市場の変化や政府の意向も踏まえて、人材派遣型ふるさと納税についての調査に力を入れています。
ここまで変化が大きいと調査の面白みも大きい
- 小坪
- 内閣府やいろんな省庁で、アイディエーションがやっている調査にものすごく価値を感じていただいていて企業版ふるさと納税の調査結果の報告のための勉強会を開催させてもらっています。過去、経済産業省、環境省、農林水産省、内閣府で開催してきましたが、この調査は自治体も企業もほとんど誰も制度の内容を認知していなかった頃から開催しているという点に大きな価値があります。
自治体も企業も、誰に聞いても9割9分知らなかった制度を今では誰でも知っていて、うまく活用しようという意向になってきています。そこの変遷というのを毎年定点で、しっかりした設問数・回答数で調査してきました。市場を動かし、制度検討に活用するという意味で非常に価値の高い調査結果にはなっているのは間違いないです。 - 坂田
- 調査結果は毎年ほぼ全てのデータを公開していて、調査結果の報告会を無料でオンラインにて開催していますが、参加者は年々増えていて、最初は20人くらいでしたが昨年は70人くらいにご参加いただきました。
アイディエーションさんからカルティブにどういった提案がありました?
- 坂田
- 提案というか示唆出しですね。「こういう風に市場変わっていませんか?」というのを仮説立てして試行錯誤してレポートしています。そして、一緒に市場の変化を話し合ってそれを報告会で皆さんに届けます。
- 波多野
- 小坪さんが肌感で予測したものを統計で見える化し、言語化して擦り合わせて一つの年次のレポートが出来上がるという流れを毎年やっています。
- 小坪
- 今年は特にアンケート調査結果から見ると認知率はあまり増えていませんでした。ただし、実施率が結構上がっています。今までアーリーアダプターとしてどう水面下で頑張るかがマーケティングでの重要課題でしたが、企業の認知・活用意向が高まってきた今は、さらにしっかりとマーケティング・営業展開することが重要になると思います。
- 坂田
- 今回は特にその提案がポイントですね。調べて見た限りだと、マスメディアを使ってのコミニュケーションが有効そうです。
- 小坪
- 最初は本当に認知の低いところから始まって、2年目から4年目ぐらいは「だいぶ伸びたな」という感覚でした。ここ数年は、認知量は伸びず実施量が上がっています。制度の延長が見えない中で、新規の企業が制度活用に踏み切れなかったと想定されます。制度の根本的なところの課題もありますし、マーケティング的な課題でもあります。
- 坂田
- 企業側のアンケートで「メリットが分かりにくい」というのがずっと断トツ一番をキープしています。この制度って長期的にwin-winの関係を作らないと分かりやすいメリットがないんです。ただ、地方創生においてものすごくインパクトが大きいのは正しいです。企業側がボトムアップで会社として動くためのメリットを伝えるというのはものすごく高いハードルなんですよ。周囲に対してのメリットはよく分かるけど、企業側のメリットはわかりにくいとも言い換えられます。決定権の強い方のアンテナが高く、深く理解をしてくれた人が音頭を取り続けてくれないと結実しない。
- 小坪
- 企業版ふるさと納税の企業にとってのメリットは、会社の規模や活用方針などによって千差万別です。地域貢献ができるという点をメリットに感じてくれる人が増えて、どんどん使ってくれたらうれしいです。

当事者意識のモチベーションの高さがプロの品質を築いていく
アイディエーションにとってこの企業版ふるさと納税の調査って他の依頼されてくる調査とかなり違う異質なものという印象ですか?
- 波多野
- 異質でしょうね。そもそも「何なの」って話になりますから。
- 坂田
- 「企業版ふるさと納税ってそもそも何ですか」という話ですよね。まだ形成されてない市場で数年で急激に伸びているのは多分この調査だけでしょう。定点でやっているものはいくらでもあるけど、ここまで劇的な違いが出てることはなかなかありません。普段の定点調査は、一部少し変化したら、なんで変わったのか物議をかもしますが、この件に関しては変わりすぎていて何が影響しているか僕らも読めない部分が大きいです。
面白みって感じられたりしますか?
- 坂田
- ここまで変化が大きいと面白みも大きいです。こんな実施率とか上がると思ってもいませんでした。「こんな変わるのか?」というぐらい変わっているので、そこはやっぱり面白い。一番面白いのは結果が出て、その結果に対して他のriver関係会社の方がお集まりいただいている定例報告会のとき「我々はこう思っている」とか「変わるとしたらどう変わるのか」や「ここはこういう数字になるのではないか」だったりを話し合うことです。
- 小坪
- それはこの調査の特徴で、出してもらったものをレポートして、最終納品する2週間くらい前にriverの直接契約ある人はみんな参加していい内部報告会をさせてもらっています。そこでアイディエーションから概要を説明してもらって、参加者がそれぞれの地域のポジションから言いたいことを言ってくれます。それをまたレポートに反映してもらえているんですよ。このフェーズを僕は大事にしています。新しい気づきがそこで生まれます。
- 坂田
- マーケットの肌感と違うレポートを出してしまったらそれはそれで分析違いなので、そこをちゃんとすり合わせできるのがこのプロジェクトの面白さです。
- 波多野
- 入社した当初からジョインしているプロジェクトで非常に思い入れがあります。毎年の市場動向を分析するのも楽しいですし、来年もどのような結果になるのか楽しみにしています。よりよい調査になるよう皆さんと試行錯誤しながら取り組むことにも面白さを感じています。
一方で、反省点もあります。回答が「その他」に寄ってしまったことがあり、もっと適切な選択肢を用意できたのではないかと悔しい思いをしました。次回の調査では挽回したいと思っています。 - 小坪
- その他が多いと、次回以降の追加する選択肢の議論が盛り上がりますね。
小坪さんから見たお二人の印象を聞かせてください。
- 小坪
- ストイックでプロフェッショナルリズムが本当に高いです。追加で急ぎで決めなければいけないけど時間がかかる案件を、明日は時間がないからと当日の夜開始の打合せで協議するということが何度かありました。
- 坂田
- 深夜に電話は何度かありましたね。一般常識的にいいか悪いかは置いといて、求めているクオリティとかスピード感に対するズレがあんまりないです。必要となればその時間にやるし、必要ないと思えばバッサリやめる、これをコミュニケーションの中でやってもらえています。委託とか受託とかじゃなく併走という感じだから楽しい。いい意味でお互いあまり気を使っていません。
- 小坪
- アイディエーションはプレイヤーの意識レベルが高く、ちゃんと求める質のレベル感を提案してきてくれます。「持ち帰って代表の確認を取ります」はほとんどないと思います。
- 坂田
- 無いですね。最終意思決定は私がしています。
- 坂田
- 倉澤さんからは2回目の調査で引き継いですぐ「来年は一人で大丈夫でしょ」と言われました。実際、そこから誰にも相談してないし、何も共有してません。2回目の調査報告会で「問題ないから来年もよろしく」と言われ、3回目以降は違和感なく倉澤さんなしでやっています。
- 小坪
- そうでしたね。1回目が倉澤さんメインで、2回目、3回目が坂田さん、4回目、5回目は波多野さんが登壇していました。コメントする余地がほとんどないくらい良かった。内容が濃いので、3回ほど聞いてもどんどん理解が深まり、勉強になりました。
アイディエーションさんからカルティブはどういう会社に見えますか?
- 坂田
- 小坪さんしか見ていないので、完全に言い表せるものではないんですが、まず一つは「楽しく仕事されてる」です。仕事をいっしょにやる上でのストレスがなくてうれしい。信頼を置いて業務を任せてくれるのでやりやすくもあります。あとは「ハードワーカー」ですね。楽しく、やりやすく、すごく働くという感じですね。ハードワークしているお互いの信頼があってこそのプロジェクトという気がします。
- 波多野
- アイディエーションの教育は「当事者意識を持て」というものなんです。「ベンチャーなんだから一人で片付けてこい」というようなモチベーションでやっています。そんな当事者意識でそれぞれが好きなようにプロフェッショナルな領域でやっています。だから戦いもしないし、うまくいっています。
小坪さんにどういう印象をお持ちですか。
- 坂田
- 小坪さん、忙しくないですか?
- 小坪
- 忙しい時もありますが、アイディエーションの問い合わせに対してはあんまり見せないようにして、できるだけ即レスに対応しています。石野さんがたくさんキャッチアップしてくれているので2人で対応しています。僕の中でも思い入れがある調査ですし重要性も高いので、この調査の価値を上げるのは優先順位が高いんです。
- 坂田
- 忙しそうですが、楽しそうに仕事をされている印象です。
- 小坪
- 特にこの調査は楽しくやっています。思い入れがあるし、止めないことを最優先にしています。資料の肌感の違いとかアウトプットしたものを見ていただいて評価してもらっていますが、そこが一番大事だと思います。アイディエーションの調査は基本的に僕の期待を超えてきてくれます。